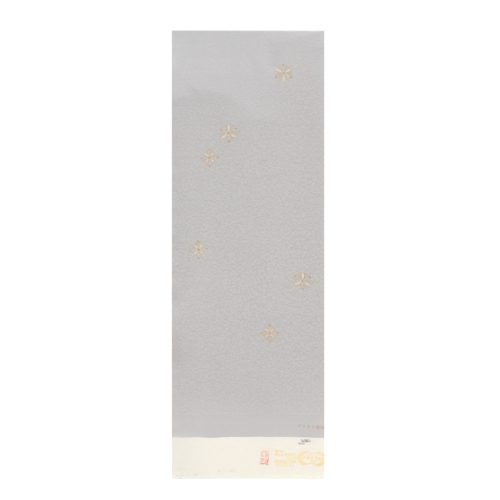4月も中旬を迎え、暖かい日が増えてきましたね。着物好きな皆さまの
中には「そろそろ単衣(ひとえ)に衣替えしてもいいのでは?」と感じ
ている方も多いのではないでしょうか。
今回は、「単衣を着始める時期」について、伝統的なルールと、今の気候
に合わせた現実的な着こなしのバランスをご紹介いたします。

単衣とは?本来の着用時期
単衣とは、裏地のついていない一枚仕立ての着物のこと。
本来、着物の季節ルールでは「単衣は6月と9月の2か月間だけ」とされて
きました。
これは、長年の季節感に基づいたしきたりですが、近年の気温上昇により、
特に5月には真夏のような日差しが感じられる日も少なくありません。
だから皆様工夫をされます。趣味でお着物を着られる方は単衣をまといま
すが、お茶をされる方はしきたりを重視される方が多く5月に単衣をとは
厳しいと考えられるので、せめてお襦袢だけでも縦絽か柄の絽を使って襟元
だけを普通にする。などなど
単衣を着始めるおすすめのタイミングは?
最近では、「体感温度」や「天気」を見ながら柔軟に衣替えをする方が増えています。
◎目安となる気温は?
☆最高気温が25℃を超える日が続くようになったら単衣がおすすめ
☆5月の連休明け頃から、気候や行き先に応じて単衣に切り替える方も多いです
屋外のイベントや日中の移動が多い日は、袷ですと暑さを感じることが多いです。そんな時は、見た目が袷に近い落ち着いた色柄の単衣を選ぶと、違和感がありま
せん。
単衣を早めに着るときの注意点【TPOに合わせて】
伝統や格式を大切にするお茶席や公式な場では、「季節を先取りしすぎない」と
いう心配りも求められます。
4月下旬~5月上旬の単衣は、あくまでも「気候に応じた例外的な対応」として、
以下のような配慮をすると安心です。
-
光沢のある薄手の絹素材など、見た目が袷に近い単衣を選ぶ
-
帯や小物は春の名残を意識したコーディネートにする
-
季節先取りになりすぎないよう、明るすぎる色や夏素材は
【小紋 京染め|型染め・飛び柄】お茶会・入学式・観劇にも品よく映える一枚こちらは、京染めの伝統技法で染められた型染めの飛び柄小紋
こちらは、京染めの伝統技法で染められた型染めの飛び柄小紋です。
落ち着いたこげ茶系の地色に、ひし形の中に唐華(からはな)文様を配した、
上品で洗練されたデザインが特徴です。菱の文様には、さらに細やかな柄が施されており、近くで見るとその緻密な美
しさに思わず目を奪われます。
同じ型紙で染めていても、飛び柄の配置や仕立て方によって雰囲気が少しずつ
異なるのも、この着物の魅力のひとつです。
唐華の向きもランダムに配置されており、全体に動きと表情を感じさせてくれます。【正絹小紋|紋意匠に飛び柄松文・プラチナ箔使用】
お茶席や観劇にふさわしい上品な一枚落ち着きと格調を兼ね備えたこちらの正絹小紋は、
紋意匠の地紋入り生地に、品よく配された飛び柄の松文(まつもん)が印象的
な一着です。
柄には繊細なプラチナ箔が用いられており、控えめな光沢が着物全体に上品な
華やかさを添えています。松は「歳寒の友」とも呼ばれるおめでたい吉祥文様。
本品ではその松文を大胆すぎない飛び柄で散らしており、茶道の席にふさわし
い控えめで凛とした印象に仕上がっています。
色柄のバランスがよく、派手になりすぎず、それでいて寂しさを感じさせない
絶妙な設計です。飛び柄の間隔や柄の控えめな華やかさから、20代〜60代以上まで、年齢を問
わず着ていただける汎用性の高いデザインです。
フォーマルすぎず、カジュアルすぎないこのバランス感は、1枚持っておくと
重宝します。これらのお着物に対してのお勧めの帯はTPOによります。
気軽なお茶席・・・・しゃれ袋や格の高い名古屋帯がいいですね
【西陣織 名古屋帯|秦生織物 謹製・市松石垣柄・白地・ラメ入り】
お茶席や街のおしゃれ着に映える、粋でモダンな一本です。
京都・西陣の老舗機屋【秦生織物(はたおりおりもの)】による、上質な
しゃれ名古屋帯です。袋帯で定評のある同織元は、裏地も含めて同じ機で
織り上げる独自の製法を持ち、そのため帯全体がしなやかで軽く、ほどよい
ハリと高い締め心地を実現しています。
【デザインの特徴として】
白地を基調に、市松に石垣柄を織り出したすっきりとしたデザイン。
部分的にラメ調の糸を織り込み、さりげなく輝きを添えることで、
現代的でモダンな印象に仕上げられています。
洗練された都会的なセンスが光る一本で、
着物初心者から上級者まで、幅広い方におすすめできる帯です。【西陣織 袋帯|秦生織物 謹製・暈し横段にペルシャ小花紋】
お茶席や華やかなパーティーシーンにふさわしい、気品ある一帯です。
京都・西陣の老舗機屋【秦生織物】謹製による、しゃれ感漂う高級袋帯です。上の小紋とは同系にはなりますが帯締めや帯揚げで全体をまとめることが出来ます
しなやかでありながらしっかりとしたハリがあり、非常に軽やかな帯地は、
まるで能装束の「水衣(みずごろも)」のようなふんわりとした風合いを持ち、締
め心地の良さと優雅さを兼ね備えています。
地色は、深みのある枯茶色(かれちゃいろ)と、
グレーを帯びた胡桃染め(くるみぞめ)が交互に織り出された横段の暈し織り。
その上を、流れるように美しく配置されたペルシャ調の小花紋様が優雅に彩り
ます。織りの立体感と繊細な配色が、控えめながらも華やかな印象を与え、
格式と洒落感を絶妙に両立させた袋帯です。淡いお色の小紋にはとても
合う帯かと思います。小紋はどちらも飛び柄となっております。
飛び柄小紋の柄合わせについて ~掛け衿や仕立ての工夫~
飛び柄小紋のお仕立てにあたっては、仕立て屋さんと綿密に相談し、柄の持っていき方にこだわっております。特に柄合わせは、仕立ての完成度や着姿の印象を左右する大切なポイントです。
飛び柄小紋は、付け下げのような厳密な柄合わせは不要とされていますが、それでも柄の位置や配置によって全体の雰囲気が大きく変わります。だからこそ、私どもと仕立て屋さんでできる限り美しく仕上がるよう、柄合わせに細心の注意を払っております。
なかでも「掛け衿(かけえり)」の柄合わせは難所です。掛け衿の中心部分で柄が不自然に途切れてしまうと、せっかくの飛び柄が不自然に見えてしまいます。そのため、柄がすっきりと見えるよう、柄を隠すか・つなげるかといった判断も慎重に行います。最終的には、柄が自然につながって見えるような配置にすることで、より美しく仕立て上がることを目指します。不自然に途切れるなら隠すように入れ込むとか色々と苦心致します。
飛び柄小紋をお選びの際には、こうした「柄合わせによる印象の違い」にもぜひご注目ください。仕立て次第で、着姿が格段に洗練されます。